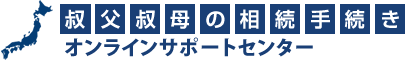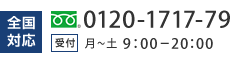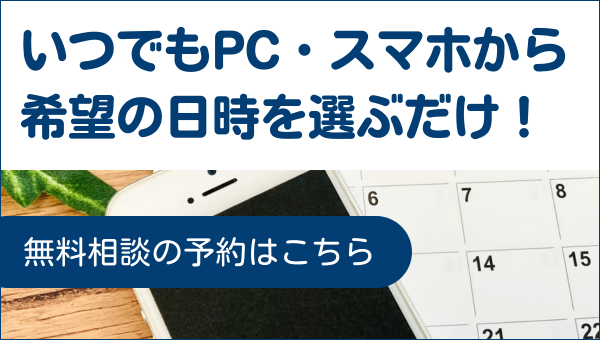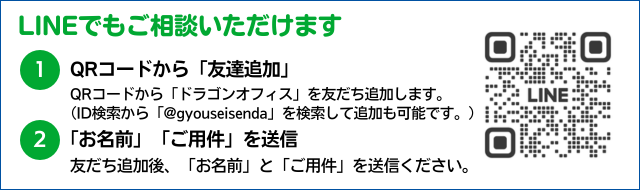叔父叔母が亡くなり自分が相続人になった際に決めること
子供のいない叔父叔母が亡くなり(叔父叔母の親も死亡しているものとします)、その叔父叔母の兄弟姉妹も先に死亡している場合に、甥姪が相続人になるケースがありますが、甥や姪が叔父叔母の相続人になった際に考えなければならないことがあります。それは、叔父叔母の遺産を相続するか、放棄するかの決定です。しかもこれは、叔父叔母が死亡し、自分が相続人になったことを認識した時から3ヶ月以内に決定する必要があります。
3つの相続方法を3ヶ月以内に決める(単純承認、限定承認、相続放棄)
叔父叔母の相続が開始され、相続人となった甥姪は亡くなった叔父叔母が残した財産を相続することができますが、相続財産の中にはプラスの財産だけではなく、マイナス財産=負債、借金などがある方もいらっしゃいます。原則的に、相続人となった甥姪はそれらの負債も相続しなければいけませんが、自分への相続が開始されたことを知ったときから3か月以内(この期間を熟慮期間といいます。) に「相続を放棄する」旨を家庭裁判所に申し立て、家庭裁判所により相続放棄を受理してもらえれば、それらの負債を負わなくてよくなります。相続放棄については、申し立てが受理されるとプラスの財産も相続できなくなりますので注意してください。
また、被相続人の財産をはっきりと把握できなく、プラスの財産とマイナスの財産が複雑に混在し、もしかするとマイナスの財産のほうが多くなるかもしれないと思われる方は、限定承認(げんていしょうにん)という手続きを家庭裁判所に取ることができます。限定承認とは、相続で得た財産の範囲内で負債を負うが、相続で得た財産よりも負債のほうが多くなってしまった場合は、はみ出た負債を負わない(責任を負わない)という手続きです。逆に、プラス財産とマイナス財産を清算し、プラス財産のほうが多くなれば、プラスのはみ出た財産を相続できます。限定承認手続きも、叔父叔母の相続に関し、自分への相続が開始されたことを知ったときから3か月以内(熟慮期間内)に手続きをします。
相続放棄の申し立ては、相続人それぞれが単独で申し立てできますが、限定承認の申し立ては、共同相続人全員が手続きに参加しなければいけませんので、少々面倒です。
相続の放棄に関しては、相続する順位の高いものから順次していきます。叔父叔母に子供がいれば、その子供は第1順位の相続人となります。子供(孫を含む)がいなければ第1順位の相続人はなしということになります。叔父叔母に子供がいたとしても、その子全員が相続放棄をしたとすると、その子(ら)は初めから存在しない扱いになり、次の順位の相続人に相続権が回ってきます。
相続人の第2順位は亡くなった叔父叔母の親ということになります。親(祖父母を含む)がいなければ第2順位の相続人はなしということになります。叔父叔母に親がいたとしても、その親全員が相続放棄をしたとすると、その親(ら)は初めから存在しない扱いになり、次の順位の相続人に相続権が回ってきます。
このような経過を辿って、亡くなった叔父叔母の相続人に甥姪がなるということも現実的にあることです。(その甥姪の親も叔父叔母よりも先に亡くなっているケース)
叔父叔母が死亡して、その叔父叔母に借金があり、その叔父叔母の子供全員が相続放棄したケースで甥姪に相続権が回ってくるというケースが一般的かと思います。
このようなケースは、甥姪のほうで相続放棄をするということを検討することになります。この場合の3ヶ月の熟慮期間は、あくまで自分が亡くなった叔父叔母の相続人となったことを認識したときからスタートしますので、その熟慮期間の起算点を遅らせることができます。
ここまで相続放棄と限定承認について説明してきましたが、相続の仕方にはもうひとつ、単純承認というものがあります。単純承認とは、亡くなった叔父叔母の財産を無限に相続するということであり、何の手続きをしなくても、自分のために相続が開始されたことを知ったときから3か月が経過すれば自動的にその効果が生じます。
また、相続人が何らかの財産を一部相続や処分をしたり、マイナス財産(負債)を今後支払う旨意思表示をすれば、それだけで単純承認の効果を生じます。ということは、きちんと相続財産を調べ上げた上、相続するかしないかを決めなければ、後になって負債が出てきた場合に困ることになります。
「不動産を相続した後に、知らない借金がたくさん出てきた」
「預金の一部を相続した後に知らない借金が多く出てきた」
このようなことにならないよう、叔父叔母の相続開始後、その叔父叔母にどのような財産があるのかをきちんと調べなければいけません。
3か月以内に相続の方法を決められないときの対処法
単純承認・限定承認・相続放棄は、自分のために相続が開始されたことを知ったときから原則3か月以内にしなければいけませんので、それほど悠長に構えている時間はありません。
民法は、相続の方法を3か月以内に決定できないときのため、家庭裁判所に「熟慮期間伸長の申立て」をすれば、その期限を引き延ばすことができるとしています。(申し立てには理由が必要です。何か月引き延ばしができるかは家庭裁判所が判断します。)
「相続財産を調べ上げたが、どうしても一部はっきりしない部分がある。」こんな方は、3か月の期限を引き延ばししてもらうよう、家庭裁判所に申し立てをするとよいでしょう。